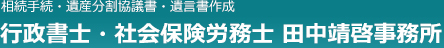他家に嫁いだ妹にはなにもやらない

他家に嫁いだ妹には何もやらない
相続相談会で、いきなりこのように切り出されたことがあります。
相談者 「実は、妹はもう他家に嫁いでいるので、遺産分けはしなくてよいだろうと考えているのですが……かりに分けるとしても少しでいいと思っていまが、問題ないですよね」
私 「どうしてそのようにしたいのですが?」
相談者「父親は遺言書は残していませんが、父親は生前から、○○家を代々継いでいくのは、長男のお前だから、そのつもりでいてくれ。また、お墓も代々まもってもらいたいといわれていました」
「つまり、お墓も含めて○○家の財産を長男の自分が引き継いでゆくのが自然だと思います・・・」
核家族化が進み、家同士の付き合いや親戚付き合いが年々薄まりつつある現在ですが、この手の話は、相続の手続きの際、まだよく出てきます。そして、これが引き金となり、想定外のトラブルが起きてしまう例も後を絶ちません。
父親の49日も過ぎたある日、長男から妹に電話がありました。
兄 「おやじの49日も終わったのでそろそろ財産の名義変更をしなければならないんだ」
妹 「私も、そろそろ今後のことについても話を始めたいと思っていたけど、どうするつもりなの?」
兄 「生前に親父といろいろ話をして大体は決めていたんだが、お前はもう嫁ぎ先の家の人間になっているし、この家のことは基本的には俺が財産も含めて全部引き継いで行くから、そのつもりでいてくれる?」
妹 「……」
兄 「郵送で必要書類を送るので、ハンコついて返してくれればいい」
妹 「ちょっと待ってよ。そんなに簡単な話じゃないでしょう」
兄 「えっ?」
妹 「お兄ちゃんは昔からそういう勝手ばかり通して、これまでは仕方なく聞いてきたけど、もういい加減にして。私の印鑑が欲しいなら、それなりの頼み方というものがあるでしょう。私だって、父さんの子という立場は全く同じなのよ」
兄 「お前、急に何を言い出すんだ?」
兄の焦りも無理はありません。いままで家のことは何事も父親と長男主導で進めてきており、今回も当然それを踏襲するのが筋だろうと兄は考えていました。ところが、どうやら事態は予想していなかった方向へ進みそうな気配です。
戦前の1940年代前半までは、日本の相続制度は家長制の考え方が色濃く残っていました。家長制のもとで「うちの家」と「よその家」は完全に区分され、その家の戸主が家の財産をすべて継承する、いわゆる家督相続が基本でした。結婚して他家に出た者は、実家の戸籍から完全に外され、実家の財産を相続する権利は原則としてありませんでした。
長男が全てを相続するような家督相続は廃止されました。兄弟すべて、均分相続の時代です!
終戦後、新しい法律によってこの制度は大きく変わりました。しかし、それによって人々の意識の隅々まで完全に入れ替わったのかというと、必ずしもそうではありません。歴史的に見れば、家督相続が当たり前の時代が長かったわけですから、そう簡単に意識は変わりません。地方に行けば行くほど、「うちの家」「よその家」といった意識が、財産を遺す世代にも受け取る世代にも、根強く残っているのです。
似たようなケースで、養子に出た兄弟姉妹について、「養子に出た子供は、実家を出たのだから相続する権利権を持っているのですか?」という質問もよくされます。
法律になじみがないと、この質問に正確に回答するのは難しいでしょう。こういう質問が浮かんでくる背景には、おそらくこんな考え方があるはずです。「養子というのは“よその家”に出された人間だから、“うちの家”については相続する権利はないのではないか?」
答えは、「養子に出ても実家の相続権は失わない」です。養子の場合は、養親と実親双方を相続することができます。間違って認識している場合が多いのですが、それは「うちの家」と「よその家」という区別を、知らず知らずのうちに先入観として持ってしまったのです。
過去にさかのぼってみれば、戦前の1940年代前半までは、日本の相続制度は家長制の考え方が色濃く残っていました。家長制のもとで「うちの家」と「よその家」は完全に区分され、その家の戸主が家の財産をすべて継承する、いわゆる家督相続が基本でした。結婚して他家に出た者は、実家の戸籍から完全に外され、実家の財産を相続する権利は原則としてありませんでした。
終戦後、新しい法律によってこの制度は大きく変わりました。しかし、それによって人々の意識の隅々まで完全に入れ替わったのかというと、必ずしもそうではありません。歴史的に見れば、家督相続が当たり前の時代が長かったわけですから、そう簡単に意識は変わりません。地方に行けば行くほど、「うちの家」「よその家」といった意識が、財産を遺す世代にも受け取る世代にも、根強く残っているのです。
ほかにも、このような意識が残っているケースがあります。養子に出た兄弟姉妹について、相続の講座などで、受講者の方からよく質問を受けます。「養子に出た子供は、もとの実家の相続権を持っているのですか?」と。
法律になじみがないと、この質問に正確に回答するのは難しいでしょう。こういう質問が浮かんでくる背景には、おそらくこんな考え方があるはずです。「養子というのは“よその家”に出された人間だから、“うちの家”については相続する権利はないのではないか?」
答えは、「養子に出ても実家の相続権は失わない」です。間違って認識している場合が多いのですが、それは「うちの家」と「よその家」という区別を、知らず知らずのうちに先入観として持ってしまったのです。
時代は大きく変わっていますので、旧来の家制度の感覚は除いて相続を考える必要があります。
→葬式代は誰がもつ
→嫁が横から「ちゃちゃを入れる」
→他家に嫁いだ妹には何もやらない
→財産は自宅のみ、しかもそこに長男家族が二世帯住宅
→相続トラブルはお金持ちの専売特許ではありません
お問合せはこちら
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
- 相続・遺言最新情報詳細
連絡先のご案内
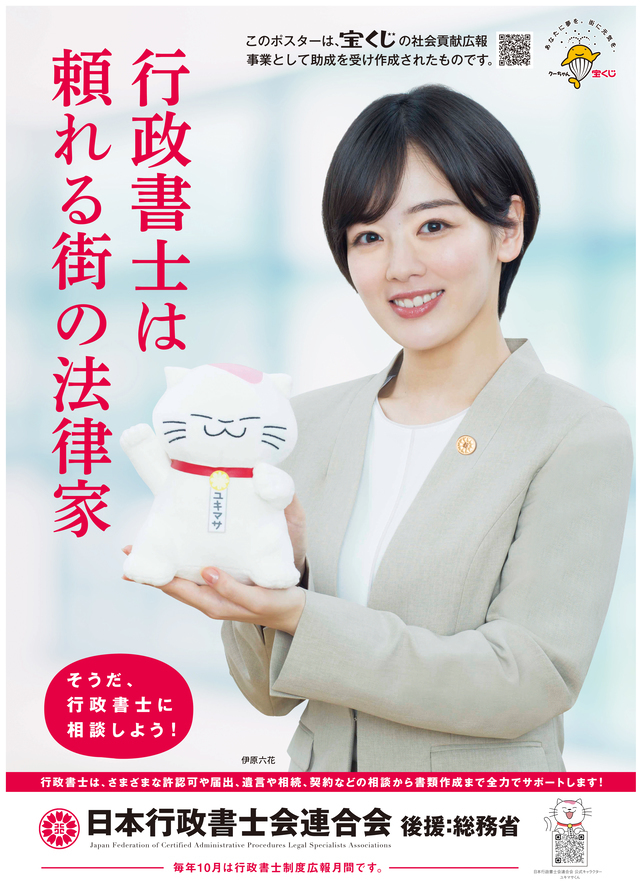
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓