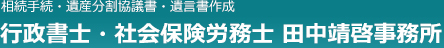借りている家はどうなる
借りていたアパートはどうなる
亡くなったかたが、借地の上に家を建てて住んでいたり、あるいは賃貸アパートやマンションを借りて住んでいたりしてその借地上の建物を相続する場合。また、アパート、マンションにそのまま相続人が住み続ける場合にも、その借地権、借家権も被相続人の遺産として、当然相続財産の対象とされます。

借地、借家の相続手続とは
この場合は、その賃借物件の貸主(地主とか大家さん)が被相続人と結んだ賃貸借契約の借主の名義を、相続人(自分)の名義に書き換えてもらえればそれで完了します。
この場合、相続は被相続人の地位の承継で賃借権の譲渡とは違いますので、貸主の承諾は不要です。貸主は原則として、借主の法定相続人がその賃借権を相続することを拒否することはできません。
また、相続を理由に相続人に賃貸借契約の名義書換え料を請求する貸主がいても、法律上はできないことになっているので拒否することも可能です。被相続人の死後、その同居人がチキンと賃料を払っていたなら、特に名義変更の必要など感じないかもしれませんが、その後のトラブルを防止するためには、名義書換えをしておいたほうが無難と思います。
亡くなった人と一緒に住んでいた相続人
亡くなった人が世帯主で、その人と一緒に住んでいた相続人(妻や子供)は無条件にその権利を承継し、そのまま居住し続けることができます。
被相続人と同居していない場合でも、その法定相続人なら被相続人が借りていた物件の賃借権を相続することができる場合があります。
この場合に相続人が複数いる場合には、それぞれの相続分割合に応じて共有することも可能です。

被相続人と同居していた内縁の妻は?
被相続人が賃借していた居住用建物に同居していた内縁の妻や養子などは、契約者本人の被相続人が亡くなった場合はどうなるでしょうか法律的には内縁の妻や養子には、原則として相続権がありません。しかし、借地借家法は他に相続人がいないことを条件に、内縁の妻などに借家権の承継を認めています。
この場合、他に相続人がいると、この借地借家法の規定は適用されません。借家権を承継し、そのまま住み続けたい場合は相続人と話し合うしかないのです。とはいっても、このような場合には裁判所が内縁の妻などの状況を斟酌し、居住権を認めることも少なくありません。
例えば、同居もしていないのに相続人の一人が内縁の妻を追い出すだけのために同意しないというようなときには十分対抗できると思います。ただし、これは借家の場合についていえるだけで借地権には例外は適用されません。
借地権を内縁の妻に承継させたいと考える被相続人の取るべき方法は、生前贈与や遺言書による贈与により借地上の建物を内縁の妻名義にしておくことが肝心です。こうすることによって、借地権を相続するのと同様の効果をえることができます。
借地借家法36条の規定です
(居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。
(強行規定です)
どんな手続きが必要
借地または借家の賃貸借契約の賃借人の名義を書き換える
- 手続き先
地主または家主
- 必要書類
地位の承継ですから、公には必要書類は必要とはしません。地主・家主から相続関係の確認のため要求されることもあるのでその場合は必要になることがあります。
- 手続き費用
名義書換料などは請求できないのが原則とされていますので、基本的には不要です。
お問合せはこちら
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
- 相続・遺言最新情報詳細
連絡先のご案内
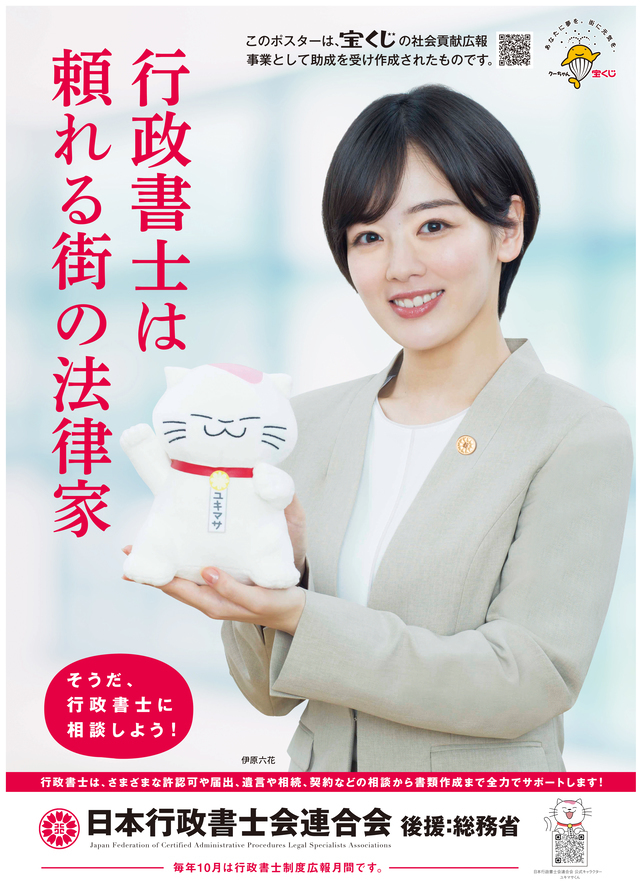
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓