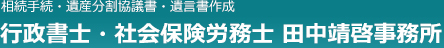【一般的には相続が開始して何もしないと単純承認とみなされる】
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限定に承継することです。
単純承認がされると、相続財産と相続人が相続する前から持っていた財産とが同一化し、被相続人の債権者は相続人の固有財産に対し強制執行ができますし、相続人の債権者は相続財産に対し強制執行ができることになります。
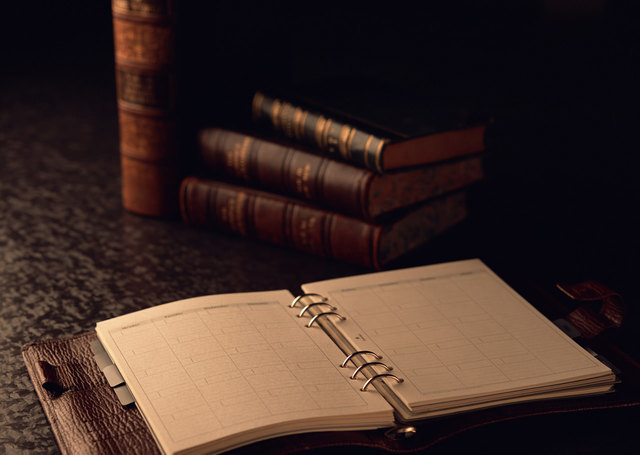
法定単純承認
民法は一定の事由がある場合には、当然に単純承認の効果が発生するものと定めており、これを法定単純承認といいます。
相続放棄や限定承認を検討する余地があると考えているときには注意が必要です。
以下は単純承認とみなされる場合の事由です。
- 1相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合
- 23ヵ月の熟慮期間を徒過した場合
- 3相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合
上の1~3の処分と徒過と背信的行為についてもうすこしくわしく説明します
1.相続財産の処分とは
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。単なる管理行為及び保存行為は処分に含まれません。
また、処分とは、財産の現状、性質を変える行為をいいますが、それには贈与や売却などの行為、故意に壊したりするような行為も含まれます。
処分の時期については、限定承認、放棄の前にされた処分のみが該当します
2.熟慮期間の徒過とは
相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。
相続人には限定承認・放棄を選択する権利がありますが、何もしないでそのまま3ヵ月が経過すると自動的に単純承認となるのです。
熟慮期間の起算点は各相続人によって異なる場合があり、熟慮期間が伸長された場合には、伸長された期間の満了時が基準となります。
3.限定承認や放棄後の背信的行為とは
相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、私的に消費したり、又は故意に、これを財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
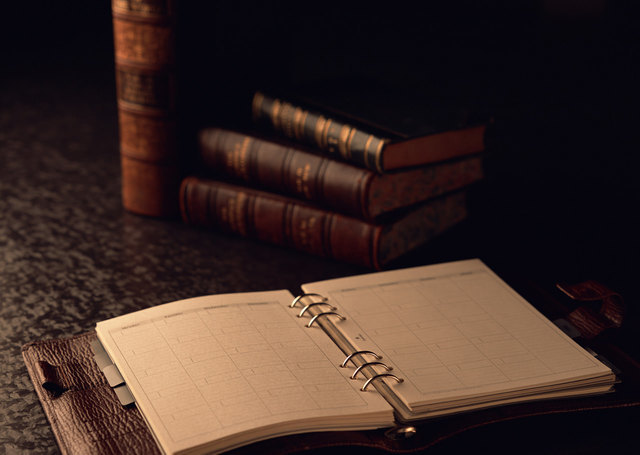
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというものです。
相続財産のうち消極財産(債務)がプラスの財産(積極財産)を上回っている場合には、相続の放棄をすればよいのですが、消極財産と積極財産のいずれが多いかが不明の場合には、限定承認をする意味があります。
「限定承認」の申し出~成立までの流れ
裁判所へお申出
限定承認は家庭裁判所へ申出する
相続人が限定承認をしようとするときは、3か月の熟慮期間中に財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申出をしなければなりません。
財産の範囲を明確にするため財産目録の調製、提出が必要とされていますが、財産の価額までは記載する必要はありません。
審判で成立
限定承認は家庭裁判所の審判で成立
限定承認は家庭裁判所が審判によって成立します。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
複数の相続人がいる場合の限定承認
相続人が数人いる場合は、限定承認は、相続人全員が共同しければできません。各相続人の熟慮期間は別々に進行するため、相続人の一人について熟慮期間が経過した場合には、その者は単純承認したものとみなされ、他の相続人が限定承認ができなくなるのではないか問題になります。
この点については、一部の相続人について法定単純承認事由が発生しても、他の相続人は、その熟慮期間内であれば、なお相続人全員で限定承認ができると考えられています。
相続放棄をした者がいる場合には、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので、その者以外の他の相続人全員が共同して限定承認を行うことができます。
限定承認の効果
限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務及び遺贈を弁済する責任を負います。すなわち、相続債権者が限定承認をした相続人の固有財産に対し強制執行をしてきた場合は、相続人はその強制執行の排除を求めることができます。
相続によって得た財産とは、相続の開始当時、被相続人に属していた財産のうち、被相続人の一身に専属しているものを除外する一切の積極財産をいいます。
たとえば、相続開始前に被相続人から不動産を譲りうけた者、また、抵当権設定者などで相続開始前に登記を具備していなかった者は、相続債権者に対してその権利取得を対抗できませんので、その不動産はいずれも相続財産に含まれます。
【承認・放棄の熟慮期間】
相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間が3か月とされる理由は、相続関係の早期安定と相続人の利益保護とのバランスに配慮したためです。相続人は、この熟慮期間内に相続財産の内容を調査して承認か放棄かの選択をすることになります。
熟慮期間の3か月の期間が経過しますと、放棄や限定承認の選択権は失われ、単純承認したものとみなされます。
熟慮期間の起算点
熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時で、したがって、相続人ごとに各別に熟慮期間が進行する場合があります。
相続人が未成年者等などの場合の熟慮期間は、その法定代理人がその未成年者等に相続の開始があったことを知った時から起算されます。
相続の開始があったことを知った時とは、分かりやすくいうと、被相続人の死亡を知ったときです。
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したとき
その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。あらたに期間がスタートすることになります。後の相続人は前の相続人が有していた相続について承認か放棄かの選択権を引継ぎますが、その熟慮期間もそのまま引継ぐとすると、後の相続人に極めて短い時間しか残らなくなるとの不都合が生じるからです。
熟慮期間の伸長
熟慮期間は、家庭裁判所への申立てにより伸長することができます。
伸長の決定は、3か月の期間だけでは、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に下されます。
具体的には、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の所在等の状況のみならず、積極・消極財産の存在、限定承認するについての相続人全員の協議期間及び財産目録の調製期間などの諸事情が考慮されることになります。
熟慮期間伸長の申立ては熟慮期間内にしなければならず、期間経過後の申立ては許されません。
▼ 一度した相続の承認・放棄は撤回できない
相続の承認及び放棄は、一度なされた以上熟慮期間中でも撤回することはできません。撤回ができるとなると法律関係を不安定にするからです。
▼ 相続放棄が認められない場合もある
たとえ、家庭裁判所に相続放棄の申述をしたとしても、次のような行為があると単純承認をしたとみなされ、相続放棄が認められない場合があります。くれぐれも注意が必要です。
- 遺産の全部、または一部を処分した場合
- 遺産の全部、または一部を隠蔽(隠す)していた場合
▼承認・放棄の取消
同様に、承認及び放棄がなされた後でも、一定の取消原因がある場合には、家庭裁判所への申立によりこれを取消すことができます。
取消しができる場合としては、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行われた場合、詐欺又は強迫によりなされた場合、後見監督人がある場合に、後見人がその同意を得ないで被後見人を代理してした承認・放棄等があります。
【相続放棄】と【限定承認】は相続人の意思を尊重し、相続人の保護をはかるためにあるものです。どちらを選択するかは、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握した上で判断する必要があります。どう判断したらいいのか、相続財産をどう把握するのか難しい場合は相続の専門家にご相談ください。
お問合せはこちら
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
- 相続・遺言最新情報詳細
連絡先のご案内
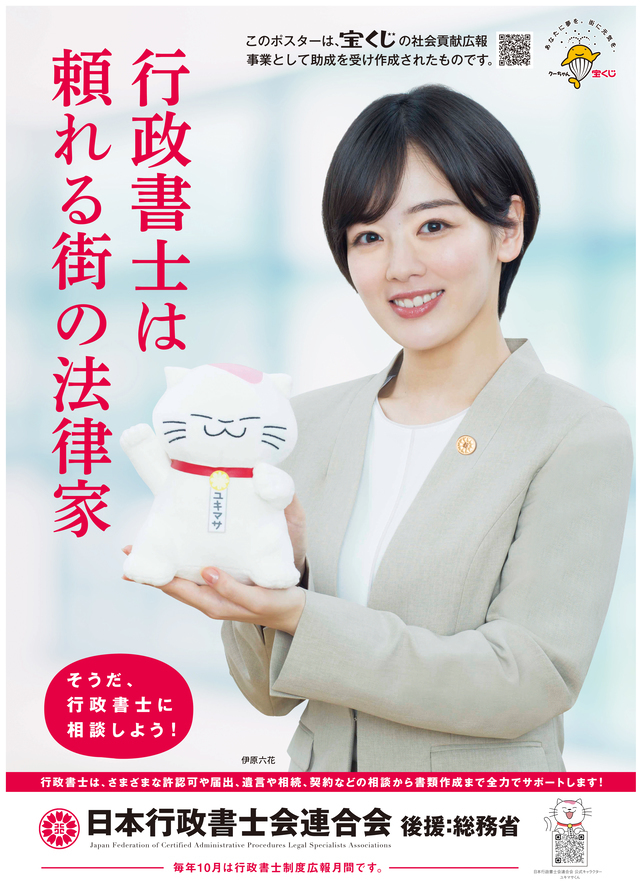
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓