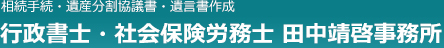取扱い業務
相続手続と遺言書の作成サポートを主業務として、このHPも情報提供しておりますが、その他、会社の設立(新設、解散、清算)、定款の作成と変更(株券発行の廃止・目的の追加と変更等)、内容証明郵便の作成、各種契約書の作成、など多方面の分野も取り扱かっています。
社会保険労務士業務としては、就業規則の作成、各種会社規程の作成、人事賃金制度の策定、労務相談と労働基準監督署対策、労働者派遣事業の許可申請・届出業務を取り扱っています
解決しなければならない問題が発生したときはお気軽にご相談、お問合せください。
相談は無料です。
相続手続き
相続手続きは、亡くなった方と法定相続人の関係、遺産の種類、遺産分割の方法、遺言書の有無などさまざまな態様があり、それによって進める手続きが異なります。
全体の概要を伺った上でとるべき手続きの説明から始めさせていただいております。
相続人の調査と確定
相続人になる可能性のある人は、亡くなった人(被相続人といいます)の配偶者以外は、子供、父母、兄弟姉妹などの血縁関係にある人です。
ただし、実際に相続人になるのは配偶者を除けば民法で゛優先順位が定められています。
また、人は生涯一つの戸籍にいるケースは少なく、結婚、養子縁組、あるいは転籍等がある異なる戸籍がつくられます。
被相続人が生前配偶者以外との間に子供を設け、認知していたらその子も相続人になります。
相続人はだれなのか全体をあきらかにしないことには、相続手続は前にすすみません。前提として相続人を確定しておくことが重要です。
相続人調査にあたっては、依頼者様からの聞き取りと戸籍謄本等を取り寄せ確定します
相続財産の確定と評価
遺産分割協議の前提条件として、何が相続財産に該当するのかを確定し、さらにその財産がいくらになるのかを評価したうえで遺産分割協議を進めることができます。
相続財産になるものとならないものを区分したうえで、それぞれの財産の相続時の評価額を算定し相続財産の総額を確定します。
書類の収集
相続手続と遺言書の作成には、さまざまな添付書類が必要です。なにを用意する必要があるのか、その書類はどこに請求すればいいのか、請求の仕方はどうすればいいのか、戸惑うことがいっぱいです。また、法定相続人がどの範囲までいるのか不明という場合もあります。
当事務所では、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所、生年月日を手掛かりとして相続手続に必要な書類の収集を代行します。
収集する書類の例
- 戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
- 住民票(住民票謄本・正本、住民票除票、住民票記載事項証明書)
- 不動産登記簿謄本(土地・建物等の登記事項証明書)
- 固定資産税評価証明書(土地・建物等の固定資産税評価額)
- 商業登記簿謄本(会社の登記事項証明書等)
具体的な遺産分割手続き
- 不動産の名義変更
- 預貯金の解約
- 株式等金融資産の解約
- 名義変更etc
遺言書の検認の申立手続サポート
自筆証書遺言があるとき、あるいは見つかったとき、そのままでは相続手続を進めることは不可能です。自筆証書遺言は裁判所の検認手続を経て、はじめて相続手続に進めることができます。
検認手続としては、申立書の作成と戸籍謄本等の必要書類を添付して申立をします。
相続放棄・限定承認の申立手続サポート
相続財産がマイナス財産(借金など)の方が多く、なにもしないでいると予期せぬ負債を抱えてしまいます。そのような場合は家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません
相続財産がいくらになるのか、財産の調査をする必要がありますが、その上で債務超過かどうか分らないときは限定承認が有効です。
相続放棄、限定承認の申立いずれも、原則として相続開始から3ヵ月以内という期限があります。相続関係者の戸籍謄本等を添付して申立を行います。
遺産分割協議と協議書の作成
遺産分割協議には相続人を確定したうえで、すべての相続人が参加して分割協議しなければなりません。さらには、相続財産の範囲と評価額を確定し、各人の相続分を決めることになります。
当事務所では、案件ごとにベストな遺産分割協議のすすめ方を提案させていただいた上で、決まった分割案について遺産分割協議書として作成します。
その他関連する業務 遺族厚生年金、共済年金の裁定請求など
配偶者が死亡し、生活費の中心か年金であった場合の遺族年金の請求も不可欠です。また、自動車の処分をどうするかも大きな課題となります。
意外と見落とされがちなこれらの手続きについても、当事務所で取扱っています。
- 遺族厚生年金、遺族共済年金の裁定請求
- 自動車の名義変更。処分
- その他、公共料金の変更手続きなど
遺言書の作成サポート
遺言書は円満な相続手続きをすすめるためには不可欠です。当事務所では依頼者の現在の状況をふまえ、なおかつ将来の親族関係の変化も見据えつつ、最適な遺言書を提案させていただいております。
自筆証書遺言の作成サポート
- 自筆証書遺言の添削
- 自筆証書遺言の起案
公正証書遺言の作成サポート
- 公正証書遺言の起案と作成サポート
- 公正証書作成の証人の手配
会社の設立(新設、解散、清算)
定款の作成・変更手続き、社会保険・労働保険の手続
法人の設立手続きとその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。当事務所は社労士事務所も開設していますので、会社設立にともなう社会保険・労働保険の新規適用、資格取得届、会社設立に関連して生ずる、労働関係諸届も代理して行うことができます。
また、当事務所では行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています。電子定款による会社定款には印紙代が不要となります。
内容証明郵便の作成代行
内容証明郵便は、相手方に対する意思表示の手段として、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、日常生活のいろいろな場面であるいは取引の場面で必要かつ有効な効果を現出します。後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等にも有効な手段となります。
当事務所では電子内容証明郵便として作成しています。通常手書きで郵便局の窓口を経由して出す、内容証明郵便は便箋一枚の字数が制限されていますが、電子内容証明郵便の場合は便箋の升目の制限はありませんので、文案も充実しさらに、料金も格安でつくることができます。
【内容証明郵便の活用事例】
- 敷金返還請求 ・貸し金返還請求 ・クーリングオフ
- 売掛金の回収催告書、 不良債権の催告書遺留分減殺請求 (相続)
- 未払い賃金の請求 ・解雇予告手当の請求
以上は一例です。内容証明郵便は書き方によって劇的な効果を生みます。当事務所ではさまざまな内容証明郵便の起案と配送手続を行います。
社会保険労務士業務
就業規則の作成
就業規則は、労働時間、賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めて、これを書面にしたものです。労働者が安 心して働くために職場の労働条件や規律を明らかにしておくことは重要であり、職場でのトラブルを未然に防ぐこともできます。(事業所の実態にマッチした最適な就業規則を作成します)
もちろん、労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する事業場では事業主は必ず就業規則を作成しなければならないとされていますし、また、10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。
人事労務管理(労務コンプライアンス体制の整備)
最近は労務コンプライアンスが話題にされますが、労務コンプライアンス体制を確立するためには就業規則だけでは事足りません。会社を運営していく上で大切なのは就業規則にとどまらない、規則・規定を整備することにあります。
適切な人事労務管理は企業の健全な発展の鍵です。例えば、未払い賃金発生の要因は気がつかないまま潜在化しています。そのためには、人事・賃金制度の診断、整備が焦眉の急です。
また、雇用契約、賃金・労働時間をはじめとする労働条件、高齢者や期間労働者、パートタイマーの雇用管理、人材の適切な配置等、働く人の労働環境を向上し、企業の生産性を高めるとともに、急増している個別労働関係紛争を未然に防ぐため、専門家の視点でそれぞれの企業に適した提案、アドバイスを通じて、経営者や働く皆様の相談に対応させていただきます。
- 就業規則をはじめとする会社諸規定の作成
- 未払い賃金発生防止のための給与関係規定の見直し
- 人事制度・賃金制度の構築
- 人事労務相談 問題社員対策 労働トラブルの防止と対策
- 労働時間・休日管理 36協定
労働・社会保険の手続き
労働保険・社会保険の適用手続並びに適用の判断が煩雑で難しいところがあります。また、給与の支給方法を変えることによって、社会保険料の見直しを図ることも可能です。当事務所では労働社会保険の複雑で多岐にわたるさまざまな事務手続きを円滑かつ適切に処理します。
- 労働保険・社会保険の新規適用及び適用廃止(会社設立時含む)
- 労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続き
提出代行、各種許認可、助成金の申請業務
人事労務に関する各種届出、助成金の申請、各種許認可の申請は煩雑で、各種要件も複雑・多岐にわたっております。手続が煩雑すぎて、中には諦めている会社もあります。社会保険労務士はこれらの必要な手続き、要件を企業の現状を確実に把握したうえで、効率よく適切に整理し円滑に処理します。
- 労働基準法、労働法に関連する各種申請書の提出
- 各種給付金、助成金の申請(雇用調整助成金等)
- 各種許認可の申請(特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業)
個別労働関係紛争の未然防止とあっせん代理
今、多くの職場で解雇、未払い賃金、セクハラ、パワハラ等のさまざまなトラブルが増えています。職場のトラブルは働く人にも企業経営者にも精神的、時間的な負担を課しお互いの効率の低下を招きます。ひいては、職場の生産性の低下、経営数値の悪化、労働条件の低下という負のスパイラルを生じます。
当事務所ではこれらの労働トラブル防止の観点から、労務診断を通じて適切な制度整備のためにアドバイスと紛争が発生した場合はその解決ならびに特定社会保険労務士としてあっせん代理も行います。
- 紛争防止のための制度整備と体制の確立
- 紛争解決のためのあっせん代理
年金相談と年金請求
年金制度は複雑すぎて、毎年政府から年金だよりが届けられる体制になりましたが、それをみても仕組みがよく理解できないというのが本音です。
また、定年間近で、定年後の働き方を年金と雇用保険の受給の仕方について適格に判断できる情報提供が適切になされていないのが現実です。
社会保険労務士は、社会保険、雇用保険、そして定年後の高齢者雇用の助成金制度のあり方等トータルに判断して適切なアドバイスができます。
- 年金相談
- 各種年金の裁定請求
お問合せはこちら
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
- 相続・遺言最新情報詳細
連絡先のご案内
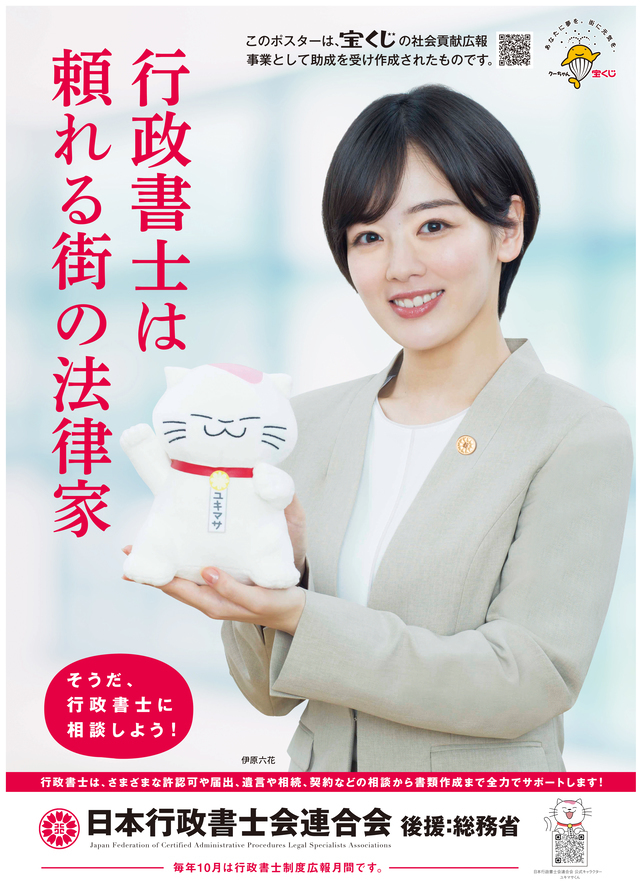
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓