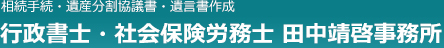葬式代は誰がもつ
遺産分割協議もいいけど、ちょっと待って! 私が立替た葬式代は誰が払うの?
かつて葬式は、故人とは関係の無い親族の友達からや会社関係など大勢参列し、規模の大きさを競うようなありさまです。最近では葬式も様変わりし、規模やスタイルも変化しつつあります。とりわけ家族を中心とした近親者のみで執り行うケースも増えています。
とはいうものの、どのような形式をとったとしても、葬儀にはかなりの費用がかかります。
そこで浮上して来るのが、それは「いったい誰が葬儀の費用を負担するのか」という、現実的なお金の問題です。
姉「やれやれ、お父さんのお葬式も何とか終えたわね。始めは、大げさでなく内輪でといっていたけど、あまり貧弱なお葬式だと周りから、何を言われるか分かったもんじゃないから。とりあえずよかったわ」
妹「祭壇もずいぶん立派だったよね。お父さんの親戚筋も納得したんじゃない?」
弟「祭壇だけじゃないよ、送迎の車にしろ、花輪にしろ、えらい立派で豪華だったよ!僧侶もあれだけいて、社葬みたいだったよ」
姉「いいじゃないの!なにかと賑やかで、派手好みのお父さんもきっと喜んでいるわ」
姉「ところで、今回の葬儀費用についてはうちが立て替えているから、みなさんも頭割りで負担してちょうだいね。お父さんの預金は解約手続きがまだ先になるし、うちもいつまでも立て替えておけるほど楽じゃないのよ」
妹「全部でいくらぐらいかかったの?」
姉「概算で450万円位だと思うけど」
妹・弟「ええッ!?」
姉「あれだけのお式だったんだから、それぐらいかかりのは当然でしょう?」
弟「当然じゃないよ!かかりすぎだよ!見栄を張るためだけに、そんな費用をかけるなんて信じられないよ。しかも、事前に何の相談もなしにだよ!俺にしたって、すぐに用立てできる額じゃないよ」
姉「いまさら何言ってるの。申込書には長男で喪主のあんたが全部サインしたんでしょ!」
妹「私はぜんぜん関わってなかったわけだし、世間では喪主がほとんど負担すると聞いていたわよ。お兄さんは喪主でもあり、これからも○○家のお墓を管理していくんでしょう。均等に負担するのはちょっと勘弁してよ、一部負担させてください」
姉「全部人任せにしといてみななに勝手なことをいってるのよ。うちだけが負担が大きいなんて呑めるわけがないじゃない……」
というわけで、父親のお葬式を無事に終えたはずの3人の遺族でしたが、トラブルの気配が濃厚になってきました。いまからこれでは、この先に待ち構える遺産分割協議が思いやられます。全員で均等に負担するというのは理屈が通るような気がしますし、事前の相談もなく、後から言われても困るというのが本音でしょうか?
さて、それでは葬式代は誰が負担すればいいのか。答えは……
正直なところ、正解はありません。実はお葬式の費用の負担については、法律では何も規定されていません。とりあえず、相続税の申告をするときには、国税庁のしおりにも一定の葬儀費用について、故人の遺産の中からマイナスして計算してもよい、という決まりがあるので、葬儀費用は故人が支払うべきものという考え方をとっているとも言えます。
しかし、これはあくまで税金の計算をする上での考え方であって、逆に故人の遺産が全く無い場合を想定すれば、それこそ誰が負担するのかは大変重要な問題になります。
相続税申告の決まりから費用負担の方法が明らかになるものではありません。これがもし、生前に発生した費用であれば、遺産のうちの債務として相続人全員で負担すべきと考えられますが、お葬式は通常、亡くなった後にしかあり得ません。最近は生きているうちに葬式を済ませてしまうという粋な方もいるようですが、これとて遺族の気持ちからすれば亡くなったあと正式な葬式をしたいという場合があれば金額の大小は別にしてやはり費用はかかります。
また、お葬式は法律で必ず行わなければならないという決まりがあるわけでもありませんのでかえって厄介です。遺された人々が自主的に行う儀式という側面が強くなります。そのため、葬儀費用の負担については複数の考え方が存在し、早い話が個々の事情によってケース・バイ・ケースということになってしまいます。
香典を葬儀費用に当てるべきだという考え方もあります。これとて、香典で葬儀費用の全てがまかなえる訳ではありません。
先祖代々の祭祀を主宰するのは長男だから、イコール喪主になっているんだから、喪主が支払うべきという考え方もあります。
このように、複数の考え方が存在するために曖昧な回答になりましたが、ひとつだけ確実に言えることがあります。上記の3姉弟のケースで、姉が主張しているような「お葬式代を全員で均等に負担しましょう」という意見は、必ずしも通るものではないということです。
ですから、お葬式の費用の負担について、見切り発車で自分だけで進めることは危険です。お葬式を執り行っていく上で、誰がその費用を負担するか。明確に決められていないという前提で、生前の本人や周囲の意見も集約しながら、慎重に進める必要があるでしょう。
どちらにしても、故人の遺産でまかなえる範囲であれば、それで清算するのがいちばん無難な解決策ではないでしょうか。
→葬式代は誰がもつ
→嫁が横から「ちゃちゃを入れる」
→他家に嫁いだ妹には何もやらない
→財産は自宅のみ、しかもそこに長男家族が二世帯住宅
→相続トラブルはお金持ちの専売特許ではありません
お問合せはこちら
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
- 相続・遺言最新情報詳細
連絡先のご案内
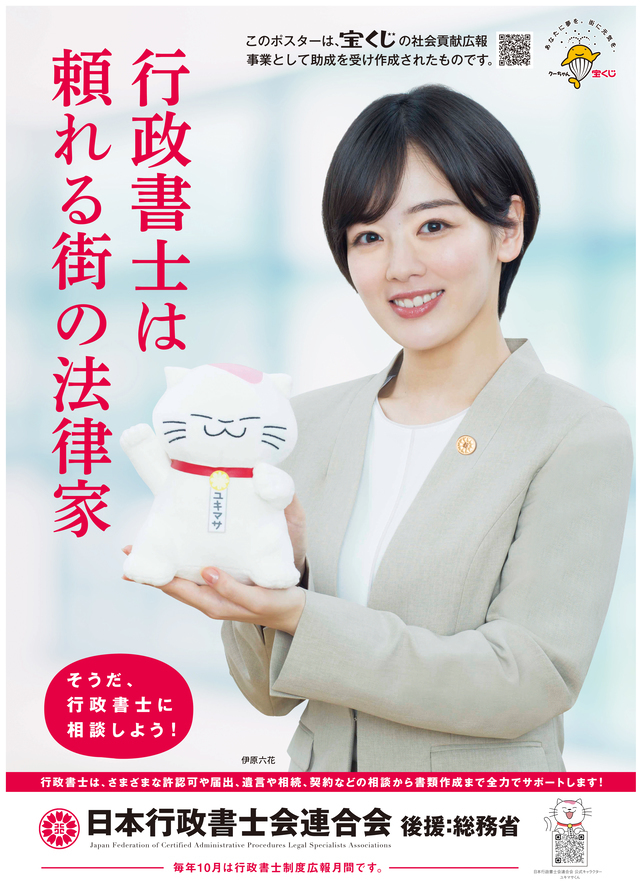
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓