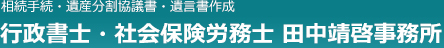特別代理人の選任手続が必要

相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者本人は協議に参加できないので、代わって代理人が協議に参加必要があります。通常、代理人には親権者がなります。
また、未成年者の両親の一人も相続人となっている場合は、相続人ではない残りの親が代理人となります。
特別代理人の選任の必要性
相続人ではない親権者がいないケース(例:夫が死んで、妻と子が相続人となるようなケース)では、親権を行使できる者がいなくなってしまったので、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立て、その特別代理人が協議に参加することになります。
親が自分の利益を優先させて、子供にとって不利益な協議が成立してしまう場合が考えられるため、親が自分の相続人としての立場と子の代理人を兼ねることは民法で禁止されているためです(利益相反)。
留意点
たとえ第三者を特別代理人に選任しても、親と未成年者という関係上、親の意向が協議に強い影響を及ぼすことが考えられます。
たとえば不動産を相続する場合でも、「どうせ管理をするのは親だし、子供にはいずれ相続で名義が移転する」と考え、特別代理人もそれに応じることが有り得ると思います。これはこれで、一理あると思いますが、これを認めると法制度が絵に描いたもちになってしまいます。
そこで、家庭裁判所では、特別代理人選任の際に、あらかじめ遺産分割協議の内容を提出させ、未成年者に不利益がないかチェックをする取り扱いもなされているようです。
相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に行方がわからず連絡の取れない者(不在者という)がいる場合、遺産分割等の相続手続きを行うことができません。
遺産分割協議は相続人全員の参加が要件とされております。また、不動産の名義換えなどの各種手続きのためにも全員の署名捺印などが求められるケースがほとんどです。
不在者財産管理人の選任
不在者がいる場合、このままでは相続手続が進行しません。そこで、相続人等は家庭裁判所に対して『不在者財産管理人』の選任を求めることができます。
家庭裁判所で選任された不在者財産管理人は、不在者の代理人的立場として遺産分割協議に参加したりします
留意点
一般的に、不在者財産管理人には弁護士が選任されることが多いようです。申し立ての際には、将来的にはこの者の報酬となる分の予納金を収める必要があります。
また、選任された不在者財産管理人は、不在者の権利を守る必要もあるため、不在者が帰ってきたときに損をするような協議内容に承諾することはできないと考えられます。そのため、法定相続分ぐらいの財産は相続させる必要があります。
お問合せはこちら
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
- 相続・遺言最新情報詳細
連絡先のご案内
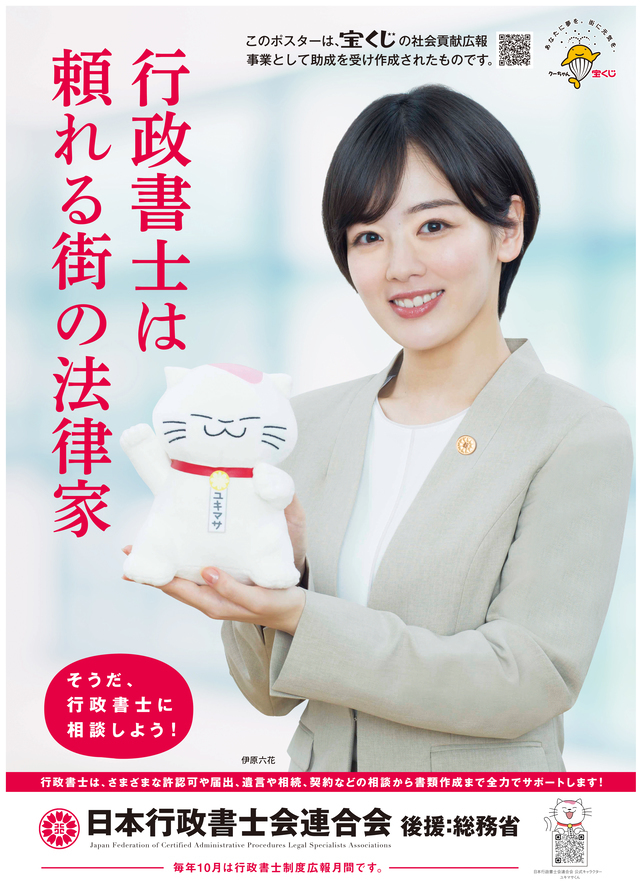
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓