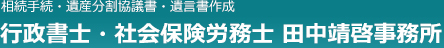特別受益と寄与分
【特別受益について】
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から贈与や遺贈を受けた場合に、他の相続人との公平を期するため、これをその本人の相続分から差し引いて計算する制度です。特別受益とされるのは
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から贈与や遺贈を受けた場合に、他の相続人との公平を期するため、これをその本人の相続分から差し引いて計算する制度です。特別受益とされるのは
- 1婚姻のための贈与を受ける
- 2養子縁組のための贈与を受ける
- 3生計の資本として、生前贈与や遺贈を受けているとき
①婚姻のための贈与とは
例えば、持参金、新居、道具類などです。額によっては、結納金や新婚旅行の費用援助なども特別受益とみなされることもある。逆に披露宴の費用などは、後に残るものでなく、また、親の都合による行事でもあるので、一概に特別受益とはみなされません。
②の養子縁組のための贈与も、ほぼ同じに考えられています。
③の生計の資本としての贈与についてはかなり広く考えられており、高等教育の学費も入るというのがいままでの考え方となっています。
相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人が、被相続人から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して
計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。
特別受益者の範囲
特別受益の持戻しをする必要があるのは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者に限られます。
そして、特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。
【寄与分について】
寄与分とは
被相続人と共同して農業や商店の経営に従事してきた相続人のように、特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、その相続人を、寄与や貢献のない他の相続人と同等に取り扱い、法定相続分どおりに分配するのは、公平を失することになります。
寄与分は、このような場合に、寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。
寄与分といえるためには、寄与行為の存在によって、被相続人の財産の維持又は増加があること、寄与行為が特別の寄与といえることが必要です。
寄与の態様
民法では、寄与の態様として、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法を挙げています。
その他の方法とは何でも入るようにとられますが、前の二つに匹敵するような方法ということになります。あたかも、特別受益とは逆の考え方で、この寄与分を差し引いたものを相続財産とみなして相続分を計算し(したがって、相続分は全員が少なくなる)寄与者についてはその相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とします。
寄与分については相続人の協議によることとなりますが、協議が調わないときや、協議ができないときは、寄与者の請求で家庭裁判所が定めることになります。
お問合せはこちら
当事務所では相続手続きと遺言書の作成、相続に関連するすべての手続きを総合的にサポートさせていただいております。全ての手続きが当事務所で完結します。安心して依頼していただけるよう適正な価格を設定しておりますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください
携帯電話:090-8082-9825
メール:yao-tanaka@nifty.com
※メールでお問い合わせ・ご相談いただいた方には、原則メールでご返事を差し上げます。
受付時間:9:00~20:00(休日も受付けます)
お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
相続手続・遺言書作成ならいますぐ、お気軽にお電話ください。
受付時間:9:00~20:00
(休日も受付けます)
営業時間:9:00~17:00
休業日:土曜日・日曜日・祝日
- 相続・遺言最新情報詳細
連絡先のご案内
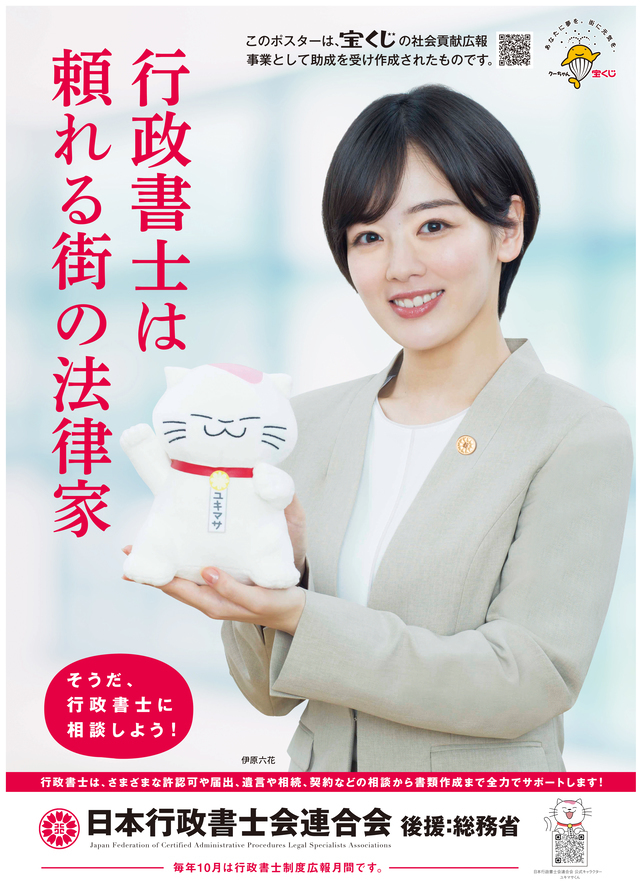
行政書士・社会保険労務士
田中靖啓事務所
住所:〒226-0005
横浜市緑区竹山3-2-2
3212-1227
代表:田中 靖啓